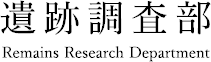大谷上ノ原遺跡
- 調査期間
- 平成29年5月~12月(予定)
- 場所
- 双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原
- 該当時代
- 旧石器・縄文・古代
- 調査原因
- ならはスマートインターチェンジの建設
大谷上ノ原遺跡は、阿武隈高地の段丘上に立地する遺跡です。これまで5回の発掘調査が実施され、1次から5次までの調査面積の合計は、34,100㎡です。今回の6次調査では、9,300㎡を対象として、発掘調査を実施する予定です。
これまでの調査によって、本遺跡は、旧石器時代、縄文時代、平安時代の複合遺跡であることがわかっています。特に、旧石器時代では、姶良(あいら)Tn火山灰(約3万年前)の上下の層から石器が多数出土しており、同時代の調査例が少ない浜通り地方において、注目される遺跡です。
大谷上ノ原遺跡の位置

下記のURLから、周辺の地図(グーグルマップ)を見ることができます。
https://www.google.co.jp/maps/@37.2840089,140.9765049,4643m/data=!3m1!1e3!4m2!10m1!1e2
5月22日のようす
5月10日から調査を開始しました。重機を搬入して、遺跡の上に堆積した土を除去(表土掘削)しています。調査区内には、元々山林であったため、多くの木根が残されていました。木根に絡む遺構に注意しながら、表土掘削及び遺構確認を進めています。

6月16日のようす
表土掘削が終了した調査区から、人力での遺構検出作業を開始しました。これまでのところ、縄文時代の土坑や奈良・平安時代頃に木炭を焼成した土坑などが見つかっています。また、縄文土器片や石器などの遺物も出土しています。
これから暑くなりますので、熱中症などに気を付けながら調査を進めたいと考えています。

7月6日のようす
遺構検出作業の結果、調査区(Ⅰ区)南東隅から古代(奈良・平安時代)の竪穴住居跡が検出され、調査を進めています。住居がどのように廃絶されたのかなどを確かめるために、土層観察ベルトと呼ばれる部分を残して掘り進めています。

8月2日のようす
住居跡の掘削がほぼ終わりました。住居内のカマドには、支脚と呼ばれる甕の底を支えるための部材が備え付けられていたことなどがわかりました。支脚は2個あり、土製と石製が並んでいました。

このことから、カマドには甕が2つかけられていたことがわかります。現在のキッチンコンロでいえば、2口タイプとなります。この後、これらの遺構を図化する記録作業を行います。

縄文時代前期の住居跡調査
過去の1~5次調査では縄文時代前期(今から約6,000年前)の集落を調査しており、今回の調査でも縄文集落が検出されました。写真1は縄文時代前期初頭の土器が出土する竪穴住居跡の調査風景です。
 [写真1]
[写真1]
縄文時代前期住居跡の調査中です。
調査前は山林でしたので、木の根と闘いながらの発掘です。ようやく土器や石器の顔が見えてきました。写真の地面に小さい白いビニール袋がたくさん写っています。この後で紹介する旧石器時代の石のかけらを入れています。
写真2は当時の生活面まで掘り下げた竪穴住居跡です。平面形は隅丸台形で、長さ約5m幅約3.5m、深さ約10㎝、小さな柱が巡るようです。柱の跡は2重になる部分もあること、炉も2基あることから、建て替えが行われたようです。家族がふえ、家が手狭になったのかもしれません。 周囲からは小型の住居跡も見つかっています。

[写真2]
写真中央の上部と下部の2個所に黒く見える部分が炉です。火をたいたときの燃料の痕跡が黒い小さな炭粒となって残っています。
よく見ると一部が赤く焼けています。大きめの石が壁際に並んでいます。何に使ったのでしょうか。
旧石器時代の調査
旧石器時代の石器群の存在も過去の調査から予想されていましたが、石器の集中地点が見つかりました。ローム層という黄色の土の中からの発見です。地層の年代から今からおよそ20,000年前のものです。白い小さなビニール袋がたくさん地面に並んでいますが、この中に発見された石器づくりに適した石を割った際のかけらを入れています。小さい破片のため、失くさないためです。この場所で石器が作られたため、石くずがたくさん飛び散ったまま残されたのです。

[写真3]
白い小さなビニール袋の中身は石器やそのかけらです。続々と出てきました。作業員の皆さん一心不乱に掘っています。

[写真4]
ローム層の地面を1cm、2cm、3cmとすこしずつ掘り下げ、今や足の踏み場もなくなってきました。

[写真5]
旧石器発見の知らせで、調査課長(写真左手前)が現地に飛んできました。
調査担当班長(左奥)は自慢げに胸をそらしています。写真の範囲で約280点の石器製作時の石の破片が出土しています。
石材は流紋岩と呼ばれる、地元の石材です。よく見ると木葉形の尖頭器(石の槍先)があることがわかります。想像すると、旧石器時代の人びとはこの槍を持って狩りをし、動物を仕留める予定だったのでしょう。狩りの道具の存在から、楢葉町の周辺にはたくさんの動物がいたことがわかります。

[写真6]
槍先となる石器が出てきました。写真右が柄につく方になります。
この槍先の形は写真8でごらんください。

[写真7]
石の破片もたくさん出ています。流紋岩(りゅうもんがん)という白い石を細かく加工していることがわかります
以前の調査では3万年前にさかのぼる楢葉町最古の石器が見つかっています。今回の調査でも期待がもてそうです。

[写真8]
木葉形尖頭器(槍先)長さ69.5mm、残念ながら先端がかけています。
[写真9]
今回調査区の別地点で出土した、切り出し形ナイフ。長さ46.5mm。
約3万年前に特徴的な石器。今後の調査でこの時期の石器群の出土も期待されます。
10月11日(水)遺跡の空中撮影を実施
発掘調査を開始してから5か月がたちました。現在の進捗状況の確認と、遺構配置、注目遺構の記録を兼ねて空中写真撮影を実施しました。工事(ならはスマートインター建設)の調整から、すでに一部調査済みの場所は、工事側に引き渡しています。
撮影は、ラジコンヘリに、フィルムカメラとデジタルカメラを搭載して行いました。
当日の天気はあいにくの曇り、しかもレーダーに映らない薄雲が低く垂れこめ、ときおり霧雨も降るという最悪の状況でした。
徐々にラジコンヘリの高度を上げながら、アングルを地上のモニターで確認しつつ、調査区全体の範囲を真上から撮影するために、高度100m近くまで上昇した時でした。モニターにうっすらとした白い靄が横切りました。オペレーターさんの「雲が下がってきている」との心配の声。遺跡の範囲は140m×240mの広範囲のためまだ高度は足りません。モニターには調査範囲全体がまだ画面に納まっていません。カメラ操作士がモニターを見ながら、操縦士に「もう少し」、「もう少し」と指示します。その時、モニターを凝視していた遺跡調査部班長から「ここ!」と指示が飛びました。直後にカメラ操作士がラジコンのシャター切る、同時に「撮れました」と力のこもった応答。
撮影はその後も続き、燃料を補充して、再フライト。画角や水平の確認、スカイの入れ具合など微調整をしながら1時間ほどの撮影は終わりました。
以下に、その時の画像の一部をご紹介します。

[写真1]
南西からの全景写真です。画面中央付近、森の中にローム層の地肌が逆S字の形に写っています。この範囲が発掘調査区です。面積では9,300㎡あります。写真画面左がわに斜めに走るのが常磐自動車道ならはパーキングエリアです。ここからスマートインターが伸びることになります。調査区は上り車線から一般道に降りるルートにあたります。

[写真2]
南から調査区の北側部分を見た写真です。画面中央やや上側では既に青色の大型重機が工事を行っているのが見えます。画面中央の地面が露出した部分が今回撮影のメイン部分です。

[写真3]
先月や先々月にお知らせした、平安時代の竪穴住居跡(画面左上方)、縄文時代前期の竪穴住居跡(中央下)、旧石器時代の石器工房跡(集中地点)(右上)などです。様々な時代の様子が同一ショットに写されています。南側からのカットになります。

[写真4]
写真3とは逆方向の北側からの写真です。手前は旧石器の工房跡、右が平安時代の竪穴住居跡、中央は縄文時代の竪穴住居跡です。
その他地面に立っている黒く見えるものは調査の都合で掘り残した大きな切り株です。

[写真5]
平安時代の竪穴住居跡です。四角い部分が地面を掘り込んだ竪穴部分、壁の一辺にはカマドが作られ、煙出し用の窪みが長く外側へ伸びています。竪穴内の床面には屋根を支える柱の穴も4本認められます。

[写真6]
こちらは縄文時代の竪穴住居跡です。隅丸の長台形の形です。内部には柱の穴や炉跡と思われる、炭粒の集中部分も認められます。竪穴の内部壁際には小さな穴が巡り、壁を支えていたと思われます。また、壁の外にもやや大きめの柱の穴も並ぶことから、この柱穴も竪穴住居跡に関連する可能性があります。
この写真撮影のため、清掃作業の際に困ったことが起きました。撮影まで住居跡を保護するために、全体に支えをいれてシートで覆っていたのですが、なんとその間に何者かによる破壊工作が行われていたのです。写真右手方向にある林の中から密かに出撃し、迂回しながら竪穴住居跡に突撃が行われていました。
犯人は、そう、モグラです。住居跡の壁が突き破られ、大事な炉跡が一部破壊されていました。写真をよく見ると、画面右手から細い小さく蛇行する線が逆時計回りに住居跡へ繋がっています。(白い矢印で示した部分)

[写真7]
こちらは真上からみた旧石器の工房跡です。長方形の区画の中に黒く見えるのが石器や石くずの破片が出土した位置です。この中で、下の写真8の石槍などが作られていました。石を打ち割るときの石のハンマーも見つかっています。
下の写真は旧石器時代の石器を並べてみました。写真の左半分が約2万年前の石器、右半分が約3万年前の石器です。

[写真8]
左側の白い石器は槍先型尖頭器(やりさきがたせんとうき)とその作りかけです。かなり大形の槍先も作っているようです。流紋岩(りゅうもんがん)という石です。風化しやすいためややシャープさにかけていますが、2万年前の当時はもっと鋭かったはずです。左上木葉形尖頭器(槍先)長さ69.5mm
右手は頁岩を主体とした約3万年前の石器群です。ナイフ形石器や石刃などがあります。こちらは対照的に割れ口もシャープな刃の鋭い石器です。