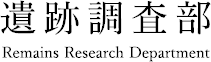桶師屋遺跡
- 調査期間
- 平成28年5月~平成29年2月(調査終了)
- 場所
- 南相馬市鹿島区北右田字桶師屋
- 該当時代
- 古墳時代
- 調査原因
- 復興基盤総合整備事業の農地整備
桶師屋遺跡は、海浜部に近い真野川左岸の自然堤防上に位置する遺跡です。試掘確認調査で溝跡と土坑が見つかり、古墳時代の土師器片や石製模造品が出土しています。
5月23日の様子
重機により、表土を除去しました。遺構はまだはっきりと見えませんが、土師器の破片が多く出土しています。

重機により、表土を除去しました。遺構はまだはっきりと見えませんが、土師器の破片が多く出土しています。
6月10日の様子
遺構がはっきり見えるよう、少しずつ土を削る検出作業をしています。古墳時代中期頃の竪穴住居跡の他、溝跡や土坑なども検出されました。遺物は土師器の他、勾玉形の石製模造品等が出土しました。

[遺構検出作業]
[出土した勾玉型の石製模造品]
7月13日のようす
古墳時代の住居跡の上に、中世末のものと思われる小穴、土坑、井戸跡が多数みつかりました。小穴は柱痕があるものや、底面に石が入っているものなど多種多様です。一つ一つ堆積土や深さを確認し、組合せを検討しています。井戸跡は8基みつかっており、中からは陶器や銭貨がみつかりました。

[小穴などを掘るようす]

[井戸跡の底からは水が湧いてきます]
8月25日のようす
中世末のものと思われる小穴の調査がおおよそ終了し、古墳時代の住居跡の調査に取り掛かりました。
写真は6号住居跡(4m×4m)で、北側を現代の攪乱により消失していますが、炉跡や遺物(土師器の杯など)を確認しました。

[6号住居跡 東から]
9月15日のようす
古墳時代の住居跡の調査を進めています。桶師屋遺跡では合計7軒の古墳時代の竪穴住居跡がみつかっています。
写真の1号住居跡はその中で最大のもので、一辺が8mほどあります。

[1号住居跡 南から]

[1号住居跡 貯蔵穴 北西から]
9月28日のようす①
現在、古墳時代の住居跡の調査を進めています。1枚目の写真は2号住居跡の貯蔵穴と考えられる穴から、土器が出土したようすです。

[2号住居跡 遺物出土状況]
9月28日のようす②
2枚目の写真は4号住居跡です。古墳時代よりも新しい、中世末のものと思われる小穴が多くあるため、住居跡も穴だらけになっています。
手前の大きな穴は井戸跡です。
中世末から建物を何度も建て替えたり、井戸を掘り直したりして人が長く住んでいたと考えられます。

[4号住居跡 全景]
10月14日のようす①
当初予定していた調査範囲1300㎡の調査が終了しました。調査した遺構は古墳時代の竪穴住居跡7軒、奈良・平安時代と考えられる掘立柱建物跡2棟、中世末から近世の掘立柱建物跡の柱穴940個、井戸跡13基、溝跡2条となりました。狭い調査区ですが遺構の密度が高く、完形の土師器や石製模造品が出土するなど、貴重な成果が沢山得られました。

[3号住居跡 貯蔵穴]
3号住居跡から土師器が出土した様子です
10月14日のようす②
2号住居跡の柱穴では、柱材の沈下を防ぐことを目的として、柱材の下に礎板と呼ばれる板が数枚敷き詰められていました。2号住居跡は一辺約7mある住居跡で、海岸平野に近く、やや軟弱な地盤につくられた建物のため、柱の基礎をしっかりと作り、丁寧な家づくりが行われていたことが分かります。

[2号住居跡 柱4]
10月14日のようす③
13基の井戸跡のうち、10号井戸跡以外は素掘りですが、10号井戸跡は丸太材をくりぬいたものを用いて井戸側としていました。井戸の構築方法として、くりぬいた丸太材を用いた井戸側の周りに細い材を配し、井戸掘形を埋め戻しています。今後作られた時代や構造を検討していきたいと思います。
今後は、11月から調査区の北東側を追加調査します。

[10号井戸跡]
11月30日のようす
新たに調査区北東側の1300㎡の調査を開始しました。表土を剥ぎ、遺構を検出したところ、溝跡がいくつも確認されました。溝跡はそれぞれ交差しており、時代が違うようですが、最も古いと考えられる6号溝跡は古墳時代後期までさかのぼります。6号溝跡からは土器も多数出土しています。他にも井戸跡や土坑、小穴群がみつかっています。

[6号溝跡]
1月10日のようす
調査区の北東側にめぐる溝跡に、平行するように細い溝跡が検出されました。溝跡と同じ方向を向いているので、溝跡に平行して作られた柵跡の可能性も考えられます。柵跡であったとすると、柵と溝が古墳時代の住居群を取り巻く景観が浮かび上がってきそうです。

[柵跡?検出写真]
1月13日のようす
3号掘立柱建物跡で検出された3本の柱穴から礎板が出土しました。礎板は、建物の重みで柱が沈まないように敷かれたもので、掘り形や規模からみて、とても大型の建物だったと考えられます。地下の水分が多いために奇跡的に残りましたが、土器などの遺物が少ないので、今後伐採年代を測定するなどして建物の年代を考えていきたいと思います。

[3号掘立柱建物跡柱穴]
1月20日のようす
10号井戸跡には丸太を半裁し刳り貫いた井戸枠(鎌倉~室町時代)が据えられています。井戸跡の調査の中で、その井戸枠の取り上げを行いました。
写真は井戸枠を傷めないように、木材を固くする溶液を薄めたものを塗布しているところです。

1月28日のようす
桶師屋遺跡の現地説明会を開催しました。天候にも恵まれ、110名以上の方が来跡されました。見学者は3班に分かれ、調査を担当した職員が、古墳時代の住居跡や飛鳥・奈良時代の溝跡、中世の井戸跡を間近で説明しました。
また、室内では出土した遺物を展示しました。ご来跡いただいたみなさんは、地域の歴史や発掘調査にいっそう興味を抱いていたようです。

[1号住居跡の説明のようす]

[10号井戸跡説明のようす]

[遺物の説明のようす]
2月10日のようす
本日をもって桶師屋遺跡の調査を終了しました。調査最終日を待っていたかのように、雪が降り積もりました。

2月22日のようす
現場での調査を終え、出土した遺物の整理などを行っています。
写真は1号住居跡からまとまって出土した土師器で、接合が完了したところです。