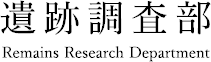植松C遺跡
- 調査期間
- 平成28年4月~平成29年2月(調査終了)
- 場所
- 南相馬市原町区上北高平字植松
- 該当時代
- 縄文時代・平安時代
- 調査原因
- 県道浪江鹿島線の整備
植松C遺跡は、南相馬市を流れる新田川によって形成された河岸段丘の縁辺に立地しています。確認調査では、縄文時代前期末から中期(約5,000~4,500年前)の土器や石製品、平安時代(約1,200年前)の土師器・須恵器や瓦が出土しています。付近には古代の寺院跡あるいは官衙跡と推定される植松廃寺跡が存在しています。また、隣接する植松B遺跡からは、古代の掘立柱建物跡が確認されています。
6月8日(水)のようす
発掘調査が開始されて1ヶ月程が経ちました。最初に調査できる面積が狭いので、人力で少しずつ作業を進めています。
写真は、掘立柱建物跡の柱穴から、古代の瓦が出土した際の様子です。この他にも、周辺からは土師器片・須恵器片や瓦・鍛冶滓などの遺物が多く出土しています。

7月22日のようす
調査区中央部分からは、竪穴住居跡や掘立柱建物跡、土師器や須恵器が捨てられた土坑など、古代の遺構が続々とみつかっています。
写真は掘立柱建物跡の様子です。人が立っている所が柱穴(はしらあな)で、大きさは一辺1m前後・深さ50~80cmと比較的大きいのが特徴です。
 [掘立柱建物①]
[掘立柱建物①]
柱穴の並び方や、柱間(はしらま)の距離から、2棟の建物跡が存在する事が分かりました。しかし確認できた柱穴は一部分で、大半は調査区の外に存在していると思われます。
なお柱穴の底面からは平安時代と考えられる土師器の杯が伏せられた状態で出土しました。

[掘立柱建物②]
8月5日のようす
平安時代の竪穴住居跡を調査しています。写真は鉄製の鎌(かま)が出土した際のようすです。
刃先が一部欠けていますが、大きさは全長20cmほどです。古いカマドを壊して埋めた部分から出土しました。
この他に完形の杯が一個伏せられた状態で出土しているので、カマドを壊す際に、祭祀等を行った可能性が考えられます。

9月27日のようす
写真1は、1軒の竪穴住居跡の貯蔵穴(ちょぞうけつ)から出土した軒平瓦(のきひらかわら)です。有蕊弁蓮華文軒平瓦(ゆうずいべんれんげもんのきひらがわら)と呼ばれる種類の瓦で、カマドを壊した際に出た焼土や粘土塊と同じ層から見つかりました。

[写真1]
写真2は、カマドから瓦が出土した際の様子です。カマドの燃焼部(火を焚いた所)に平瓦や丸瓦の破片が敷かれていました。しかし、瓦に2次的に火熱を受けた痕跡がないことから、カマドの機能が停止した段階で瓦が敷かれたことが考えられます。

[写真2]
これらの瓦は、植松C遺跡の西に所在する入道迫窯跡(にゅうどうさくかまあと)で焼かれたものと共通する特徴を持っており、ここで焼かれた瓦は隣接する植松廃寺に供給されたことがわかっています。植松C遺跡で出土した瓦は、本来植松廃寺で使用されたものを転用したと想定されます。
10月19日のようす
調査区南側に位置する、縄文時代の遺物包含層(いぶつほうがんそう)の調査に本格的に着手しました。まだ表土を剥いで掘り始めた段階ですが、すでにたくさんの縄文土器や石器などが出土しています。
写真は土偶が出土した際のようすです。

11月8日のようす
引き続き縄文時代の遺物包含層を調査しています。毎日、縄文土器をはじめとした膨大な量の遺物が出土しています。(写真1)

[写真1]
また、変わった土製品がみつかりました。(写真2)厚さ1cm程度の薄い板状で、表裏に1mmほどの非常に細い沈線で文様が描かれています。一緒に出土した土器の破片とは明らかに異なる文様であり、土偶と思われます。本来は顔などの表現があったものと思われますが欠損しています。今のところ福島県内で類例は確認できておらず、非常に珍しい土偶です。

[写真2-1]

[写真2-2]
12月15日のようす
順調に縄文時代の遺物包含層の調査が進んでいます。出土した遺物は整理箱ですでに200箱を超えています。ほとんどが縄文土器ですが、石器も多く出土しています。
中には5cm程の石槍(写真1)や、アクセサリーとして使われた3cm程の垂飾り(写真2)とみられる石製品なども確認されています。

[写真1]

[写真2]
1月17日のようす
1月17日に南相馬市労働福祉会館で、県教育庁文化財課主催の「植松C遺跡 発掘成果報告会」が開催されました。当日は地区の方々や、地元の文化財関係者含め多くのみなさんにご参加頂きました。当財団担当職員から発掘の成果を、スライドを使用して報告しました。また、出土した遺物を展示し、中でも高さ60cmを超す、大形の縄文土器に注目が集まっていました。
このような形で地域のみなさんに調査成果を報告できたことは、とても有意義であったと思います。

[写真1]報告会の様子

[写真2]出土遺物の展示
2月10日の様子
本日をもちまして、植松C遺跡の発掘調査は終了しました。約10ヶ月間にわたる調査の結果、縄文時代・平安時代という2つの時代にまたがる遺跡である事がわかりました。
縄文時代については、当時の人々が住んでいた竪穴住居跡などは確認されませんでした。しかし、調査区の南端に近い谷から、非常に多くの縄文土器や土偶、石器や石製の耳飾りなどが出土しました。出土した遺物の量は、整理箱で235箱ほどになります。土器の時期は、縄文時代前期後葉から中期前葉(約5,000~4,700年前)です。中には、北陸・関東・北東北といった各地域の特徴が認められる土器や土偶も出土しています。谷には遺物のほかに、炭化物や、動物や魚類のものとみられる骨片、焼け土などが大量に混ざった土が堆積していました。おそらく、調査区の周辺に住み続けた縄文人が、住居を造った際に出た土や、壊れた土器、食物残滓などを長年にわたって廃棄した場所と考えられます。
平安時代は、竪穴住居跡11軒、掘立柱建物跡6棟、土坑15基、溝跡3条が確認されました。なかでも掘立柱建物跡の柱穴は、一辺1mほどと規模が大きい特徴があります。これは官衙跡(かんがあと:当時の役所)や、寺院跡で確認される建物跡と同じ特徴をもっています。大半の柱穴では柱材が抜き取られ、埋め戻された様子が確認されました。
竪穴住居跡は一辺が約4~5.5mの正方形で、カマドを備えています。ほとんどの住居跡からは土器の他に、瓦が出土しました。なかでも3号住居跡からは、カマドの焼面に敷かれた状態で瓦が出土しました。植松C遺跡の東側には、古くから瓦が採集されてきた「植松廃寺跡」が存在します。今回の調査で出土した瓦は、植松廃寺跡で採集されたものと同じ特徴を持っており、植松廃寺跡で使用された瓦、あるいは植松廃寺のために生産された瓦を転用したことが窺えます。
これらの事から、今回の調査で確認された平安時代の遺構群は、建物跡の規模や、出土した遺物の特徴などから、植松廃寺跡に関連する建物群と、植松廃寺跡に関連した人達の営んだ集落であった可能性が考えられます。
今後は報告書作成に向けて、出土した遺物や調査した遺構の図面を整理する作業を行います。現場ではわからなかった、新たな発見が今後も続く事が期待されます。

[写真1]上空からみた植松C遺跡

[写真2]大形の掘立柱建物跡

[写真3]竪穴住居跡から出土した土器や瓦

[写真4]出土した軒平瓦

[写真5]縄文土器が出土した様子

[写真6]遺物包含層を調査中